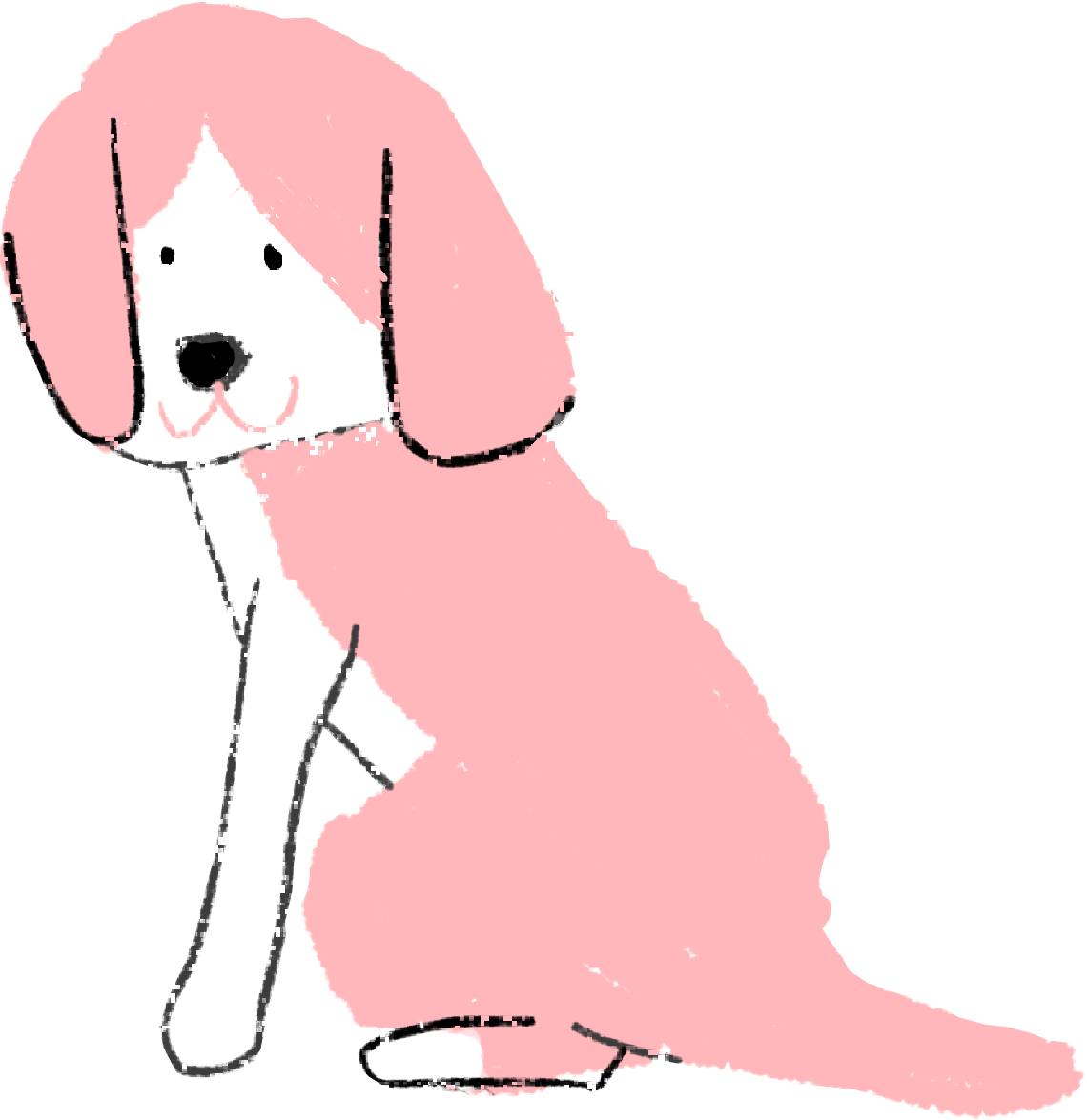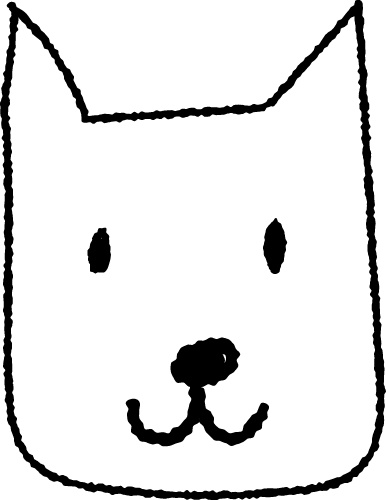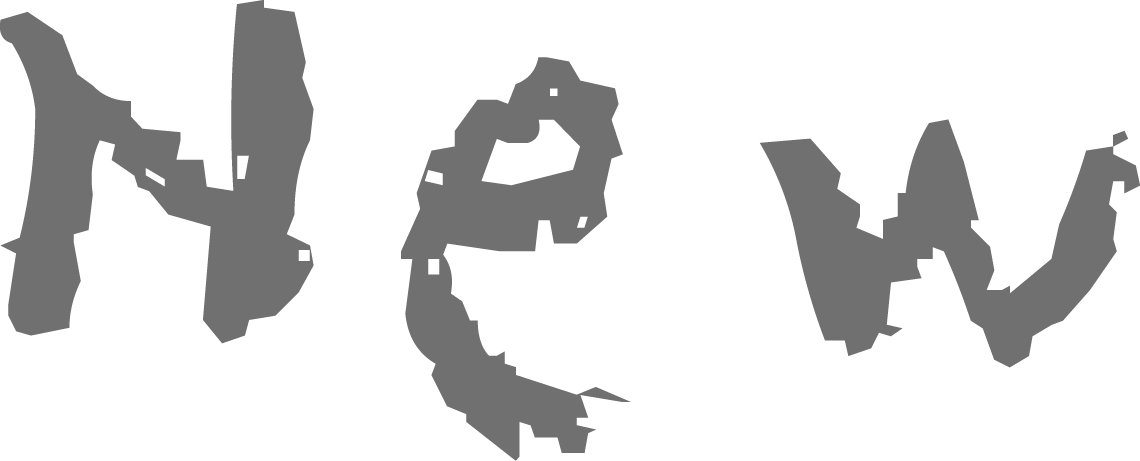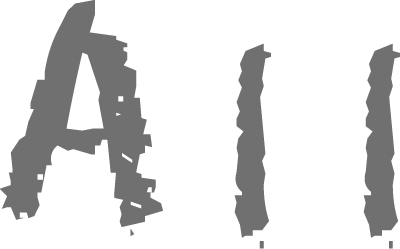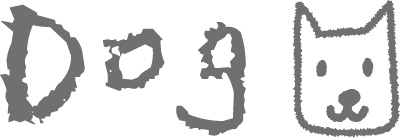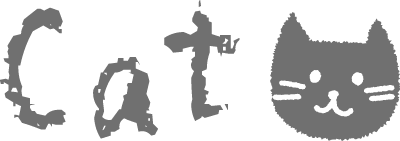犬の検便で分かる病気とは?

便の中にはさまざまな情報がたくさん詰まっています。愛犬のお腹の調子が悪いときは、検便で原因を確かめましょう。

検便で小腸・大腸・膵臓の異常も分かる
動物病院で行われる犬猫の便検査は、寄生虫を調べるイメージがあります。でも、それだけではありません。便の状態から小腸や大腸、膵臓(すいぞう)などに異常がないかも確認できます。
便は消化や吸収されなかった食べ物の残骸です。一概に便の量が多いから健康、少ないから不健康ではありません。排出される量は食べているものによって違ってきます。顕微鏡で見ると、食物の残りかすのほか、消化液や胃腸の細胞、腸内細菌などが見られます。
犬の便の形状・色・ニオイから分かること
動物病院では、まず見た目のチェックから行います。便の形状からは、腸の消化や吸収、運動状態が分かります。量も重要ですが、固さや形も大切。固形便なのか、形はあってもゆるい軟便、下痢状の水様便なのか。便の状態がどれに該当するか確認します。
もうひとつ大切なチェック項目が便の色とニオイです。良好な健康状態の便の色はだいたい黄褐色です(食事内容によって多少異なります)。下痢をすると黄緑色に変色します。白っぽい、異様に黒い、水分がほとんどないなどの状態は何らかの異常を示すサイン。また、便に血が混じっていると小腸や大腸の異常が想定されます。
便のニオイにも情報があります。腐ったニオイや酸っぱい感じのニオイは要注意。脾臓や小腸・大腸に問題があるかもしれません。

犬の検便、2つの検査方法
動物病院で主に実施される検便には直接法と集虫法の2通りがあります。
直接法は生理食塩水で便を希釈して顕微鏡で見る方法です。腸内細菌のバランス・活性や寄生虫の卵、小腸・大腸の細胞などが発見できます。その一方、一部の少量の虫卵などの発見はしにくい面があります。
集虫法は便を溶かした飽和食塩水の上澄液を顕微鏡で観察します。わずかな虫卵を発見できる一方、細菌や細胞による症状の発見には適していません。
注意点は、ペットに寄生虫がいても1度の検便では発見できないこともあること。定期的な検便で駆虫行うことが大切です。動物病院へペットの便を持参する場合は、できるだけ新しいものを持って行きましょう。その際は乾燥させないようにしてください。
SHARE